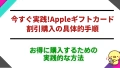図書カードNEXTは、紙の図書カードと異なり、QRコードとPINコードで書籍や雑誌を購入できる電子ギフト券です。スマートフォンでの利用を前提にした新しいスタイルの読書支援ツールとして、プレゼントや景品などで幅広く活用されています。
しかしこの便利な仕組みが、近年詐欺グループに悪用されるケースも増えてきました。とくに「コードを送ればすぐに使える」という特徴が、他のギフト券同様、詐欺に悪用されやすいポイントになっているのです。
この記事では、図書カードNEXTの基本的な使い方や残高確認方法に加え、よくある詐欺の手口やその防止策、さらに安全に現金化するための方法まで、実用的にまとめて解説します。

1. 図書カードNEXTとは?

図書カードNEXTは、従来の紙タイプの図書カードに代わるQRコードベースの電子ギフト券です。
全国の図書カード加盟書店で、書籍・雑誌・一部の文具購入などに使えるほか、スマートフォンから簡単に残高確認ができる点が特徴です。
ここでは、基本的な使い方から入手方法、現金化の可否までを順番に見ていきましょう。
1-1. 基本情報と使い方
図書カードNEXTは、以下のような特徴を持つ電子ギフト券です。
【主な特徴】
- QRコードとPINコードが印字されたカードタイプ
- 加盟書店で読み取ってもらうことで支払い可能
- 利用ごとに残高が減るプリペイド方式
- 有効期限は発行から10年間
書店での利用時は、スマホに表示されたQRコードを提示するか、カードを店頭で読み取ってもらうだけで支払いができます。
1-2. 購入方法と種類
図書カードNEXTは、主に以下のような方法で入手できます。
【主な入手方法】
- 書店や文具店などの店頭購入
- オンラインストア(図書カードNEXT公式サイトや一部通販サイト)
- プレゼントやキャンペーンの景品として受け取る
券種は500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円などがあり、企業向けのカスタムデザインも存在します。
1-3. 残高確認の方法と注意点
図書カードNEXTは、カード裏面のQRコードとPINコードを使えば、誰でも残高確認が可能です。
【確認手順】
- 図書カードNEXT公式サイト(https://www.toshocard.com/)にアクセス
- 「残高照会」ページを開く
- QRコードを読み込むか、PINコードを入力
- 残高と利用履歴が表示される
この仕様により、カードの登録なしでも有効かどうかが判別可能となっています。ただし、偽サイトを使ってPINコードを盗み取る詐欺には要注意です。
1-4. 登録やチャージの仕組みは?
図書カードNEXTは、チャージ型ではなく「使い切り型」のプリペイドカードです。
クレジットカードのように残高を追加することはできず、額面分を使い切ったら終了というシンプルな仕組みです。
また、個人アカウントに登録して管理する機能はなく、紛失時の補償なども原則ありません。
誰でも使える=誰にでも盗まれうる性質があるため、管理には注意が必要です。
1-5. 現金化できる?買取率や条件について
図書カードNEXTは、未使用かつPINコードがわかる状態であれば、ギフト券買取サイトでの現金化が可能です。
【現金化の条件】
- PINコードとQRコードが明瞭な状態で提示できる
- 使用済みや残高ゼロの場合は不可
- 画像が不鮮明・加工済みだと買取不可になるケースもある
【買取相場(2025年現在)】
- 買取率:約70〜75%
Amazonギフト券やPayPayポイントなどと比べるとやや低めの水準ですが、需要が安定しており現金化自体は難しくありません。
次章では、この図書カードNEXTが詐欺にどう利用されてしまうのか、実際に多い手口を詳しく解説していきます。
2. 図書カードNEXTを狙った詐欺の手口

図書カードNEXTは「登録なしで使える」「コードを送れば誰でも利用可能」という特性から、詐欺グループにとっても非常に“都合のいい”ギフト券といえます。
そのため、他の電子マネーやギフトカードと同様、図書カードNEXTも巧妙な手口で詐欺に利用される事例が増加しています。
この章では、よくある5つの詐欺手口を紹介し、どのような点に注意すべきかを解説します。
2-1. 架空請求や脅迫によるコード要求
最も古典的かつ依然として多い手口が、「未納料金がある」「裁判になります」などと脅してコードを送らせる架空請求型の詐欺です。
【典型的な手口】
- SMSやメールで「有料サイトの利用料が未納」と通知
- 「本日中に支払わないと法的手続きに入る」と脅迫
- 「コンビニで図書カードNEXTを購入してPINコードを送れ」と指示
このような連絡は、すべて詐欺であり、絶対に応じてはいけません。
図書カードNEXTは支払いに使えるような正規の請求手段ではなく、公共機関がこのような方法を取ることはあり得ません。
2-2. 偽物サイトで残高確認を装った詐欺
図書カードNEXTには「PINコードを入力するだけで残高照会できる」特性があるため、偽の残高確認サイトに誘導してコードを盗み取る手口も非常に多いです。
【詐欺の流れ】
- 検索やSNSで「図書カードNEXT 残高確認」と検索
- 偽サイトが広告などで上位に表示される
- 本物そっくりの入力画面に誘導
- PINコードを入力した瞬間に詐欺グループが残高を使い切る
この手口は見た目が非常に巧妙で、URLをよく確認しないと本物と区別がつかないこともあります。
残高確認は必ず図書カードNEXTの公式サイト(https://www.toshocard.com/)から行いましょう。
2-3. 高額買取を騙る個人取引トラブル
SNSやフリマアプリで見かける「図書カードNEXT高価買取します」といった投稿には注意が必要です。
実際には、コードを送った直後に音信不通になる詐欺被害が多数報告されています。
【よくあるパターン】
- 「買取率90%!即振込!」などの甘い条件で誘導
- LINEやDMでやり取りし、「先にコードを送って」と指示
- コード送信後、振込がされずブロックされて終わり
図書カードNEXTは登録不要で誰でも使えるため、コードを奪われたら終わりです。
個人取引は避け、信頼できる買取業者を利用するのが鉄則です。
2-4. 使用済みカード画像の偽装販売
もうひとつ多いのが、すでに使い終わった図書カードNEXTを“未使用”として画像で販売する詐欺です。
この手口は特にフリマアプリや掲示板で見られます。
【この手口の特徴】
- 使用済みのカードの画像を「未使用です」として出品
- PINコードの一部を隠して画像だけ送り、信頼を得る
- 購入者がコードを入力すると「残高なし」の表示
図書カードNEXTは見た目では使用済みかどうかがわからず、登録前でも確認できるという仕様が逆に悪用されやすい点に注意が必要です。
2-5. なぜ図書カードNEXTが狙われるのか
他のギフト券と比べても、図書カードNEXTは詐欺グループから狙われやすい特徴を多く持っています。
【狙われやすい理由】
- PINコードさえあれば即座に使用可能(匿名性が高い)
- 残高確認は誰でもでき、コードの有効性を騙しやすい
- 利用にアカウント登録が不要=盗んでも足がつかない
- 利用先が書店に限られており、一般的な詐欺対策が追いついていない
- コンビニなどで手軽に入手でき、指示しやすい
このような理由から、図書カードNEXTは「ターゲットとしてちょうどいいギフト券」と考えられているのです。
次章では、こうした詐欺に巻き込まれないために日常でできる具体的な対策を、わかりやすく解説していきます。
3. 詐欺を防ぐための5つの対策

図書カードNEXTは便利な電子ギフト券ですが、「誰でも使える」「残高確認が簡単」という特性が詐欺に悪用されやすい原因となっています。
しかし、事前に基本的な知識と対策を身につけておくことで、被害をほぼ確実に防ぐことが可能です。
この章では、特に意識すべき5つの対策を紹介します。身の回りの人にもシェアしながら、被害ゼロを目指しましょう。
3-1. 支払い要求には絶対に応じない
まず最も重要なのは、「図書カードNEXTを買って送って」と言われたら、それは100%詐欺だと断言してよいことを知っておくことです。
【詐欺でよくあるフレーズ】
- 「有料サイトの料金が未納です」
- 「あなたのアカウントが不正利用されています」
- 「保証金として図書カードを購入してください」
このような要求が来た場合、その時点でやり取りを中断し、連絡を遮断することが重要です。
公共機関や正規企業が、図書カードNEXTなどのギフト券で支払いを求めることは絶対にありません。
3-2. コンビニでの購入時に注意すべき点
詐欺グループは「いますぐ買ってこい」と被害者を急がせ、冷静な判断をさせないように誘導します。
そのため、コンビニでギフトカードを購入するときの意識づけが大切です。
【チェックすべきポイント】
- 誰かと電話やLINEをしながら買っていないか?
- 購入理由を聞かれても曖昧に答えていないか?
- レジ横にある「ギフトカード詐欺注意」のポスターを見落としていないか?
店員が「詐欺ではないですか?」と声をかけるのは親切からの行動です。 少しでも不安を感じたら、購入を一度ストップしましょう。
3-3. 偽物サイト・なりすましの見抜き方
最近では、図書カードNEXTの残高確認ページを装った偽サイトも出回っており、そこにPINコードを入力させて盗む手口もあります。
【見分けるポイント】
- URLが公式サイト(https://www.toshocard.com/)と一致しているか?
- ページの日本語が不自然ではないか?
- 入力フォームが広告バナーのような位置にないか?
- 常時SSL(https://で始まる)になっているか?
【対策】
- Google検索よりも、ブックマークやQRコードから公式にアクセスする習慣をつけましょう。
- 不明なリンクは絶対にクリックしない、という基本姿勢が重要です。
3-4. 家族・友人と詐欺情報を共有する
詐欺被害は、「誰にも相談せずに一人で判断したとき」に発生しやすい傾向があります。
だからこそ、日常的に家族や友人と「詐欺について話す習慣」を持つことが、最も有効な防止策のひとつです。
【共有しておきたいポイント】
- ギフトカードで支払いを求められたら絶対に詐欺
- 見知らぬ連絡が来たときは、まず誰かに相談する
- おかしいと感じた時点で、遠慮せず「教えて」と言える雰囲気を作る
特に高齢の家族や、ITに不慣れな人ほど「相談するタイミング」を失いやすいため、普段から話題にしておくことが大切です。
3-5. 年齢別に異なる詐欺の傾向と注意点
詐欺の手口は、ターゲットの年齢やネットリテラシーに応じて変化します。年代別に意識すべきポイントを押さえておきましょう。
【年代別の詐欺傾向】
- 10代〜20代: SNSでの個人取引・高額買取詐欺が中心
- 30代〜50代: 架空請求・仕事や行政を装った詐欺が多い
- 60代以上: なりすまし・孫を騙る詐欺が目立つ
【それぞれの対策】
- 若年層には「ギフト券を先に送らないこと」を強く伝える
- 中年層には「公的機関がギフト券で支払いを求めることはない」と再確認
- 高齢層には「相談をためらわない環境」を用意する
こうした対策を取ることで、詐欺の隙に付け込まれるリスクを大きく減らすことが可能になります。
次章では、万が一詐欺に遭ってしまったときの具体的な対応方法や相談先、証拠の保全について詳しく解説します。
4. 被害に遭ったときの正しい対応

どれだけ注意していても、詐欺の手口は巧妙です。「やってしまったかもしれない」と思った時点で、すでに被害が発生している可能性があるという認識が大切です。
しかし、焦らず冷静に対応すれば、被害を最小限に抑えられる可能性も残されています。
この章では、図書カードNEXTを使った詐欺に巻き込まれてしまった際に、とるべき行動と相談先、証拠の残し方までを5つのポイントに分けて解説します。
4-1. 初動でやるべきことと証拠の残し方
まずは、すべてのやり取りや購入履歴などの証拠を保存しましょう。
「とりあえず消す」はNG。トラブルの全容を把握するためにも、証拠は非常に重要です。
【残すべき証拠】
- SMSやLINE、メールなどのやり取りのスクリーンショット
- 購入した図書カードNEXTの画像(表面・裏面・PINコード)
- 店頭で購入した場合はレシートや購入日時のメモ
- 相手の連絡先、アカウント名、使用した媒体(X、インスタ、LINEなど)
この段階で残高がまだ使用されていない場合は、すぐに図書カードNEXTの公式窓口へ連絡することで対処できる可能性もあります。
4-2. 図書カードNEXT公式への相談方法
図書カードNEXTに関する問題は、まず発行元である「日本図書普及株式会社」への相談が基本となります。
【公式サイト】
https://www.toshocard.com/
【対応内容の例】
- 残高の使用有無の調査
- 不正利用の報告受付
- 利用停止や再発行の可能性(状況に応じて)
ただし、登録制ではない性質上、使用後のカードについては補償が難しいケースもあります。 早期連絡が鍵になります。
4-3. 警察・消費者センターへの相談手順
金銭的な被害が発生した場合は、必ず公的機関にも報告しましょう。 被害の記録を残すことで、再発防止や他の被害者の救済にもつながります。
【相談先】
- 警察署(サイバー犯罪対策係)
→ 被害届の提出や、捜査の対象になる可能性も - 消費生活センター(188・いやや)
→ 詐欺内容に応じたアドバイスや相談受付 - 国民生活センター(ウェブ相談可)
→ ギフト券詐欺に関する情報共有も行われている
警察や相談窓口へは、状況を正しく・時系列で説明することが重要です。前述の証拠を整理しておくとスムーズです。
4-4. 被害内容を正しく伝えるポイント
「何が起きたのか」を正しく伝えることで、サポートや公的機関の対応もスムーズになります。
【まとめておくべき項目】
- 被害に気づいた日とやり取りの開始日
- 使われた連絡手段(LINE、X、Instagramなど)
- 詐欺相手が提示してきた内容や条件
- 購入した図書カードの券種・金額・コード番号(部分的に)
- 残高が使われたタイミング(あれば)
感情的になりすぎず、客観的な事実を淡々と伝えるのがコツです。
4-5. 二次詐欺や返金詐欺への注意点
詐欺被害に遭った直後、別の詐欺師が「返金します」「取り戻せます」と“善意”を装って近づいてくるケースもあります。これは二次詐欺の典型パターンです。
【二次詐欺の例】
- 「残高を回復するには別のギフト券が必要です」
- 「弁護士を紹介するので、まず費用を払ってください」
- 「PlayStationサポートです。補償申請にはコードが再度必要です」
このような話に一切応じてはいけません。 公式窓口や公的機関以外からの申し出は、基本的に詐欺と疑ってかかるべきです。
次章では、使い道がない図書カードNEXTを安全に現金化したいときに活用できる、信頼できる現金化の方法と注意点を詳しく紹介します。
5. 図書カードNEXTを安全に現金化する方法

図書カードNEXTは、書籍購入に便利なギフト券ですが、「本はあまり読まない」「使う機会がない」という人にとっては、現金化という選択肢も有効な手段です。
ただし、個人間での売買は詐欺の温床となりやすいため、安全性を重視した方法で現金化することが重要です。
この章では、図書カードNEXTを現金に換えるための安全な手順と、よくある失敗を避けるための注意点について詳しく解説します。
5-1. 未使用コードであれば現金化可能
図書カードNEXTは、PINコードとQRコードが未使用である限り、買取業者を通じて現金化が可能です。
【現金化の条件】
- カードが未使用である(残高が満額)
- PINコードとQRコードが判読可能な画像がある
- 使用履歴に不審な形跡がない(照会されすぎていないなど)
特に図書カードNEXTは、残高照会が誰でもできる仕様のため、コードの状態が確認されすぎると「リスクが高い」と判断され、買取不可になる場合もあります。
5-2. 優良な買取業者を選ぶための基準
現金化の成否は、どの業者を選ぶかに大きく左右されます。 特に図書カードNEXTはAmazonギフト券などに比べて買取率がやや低いため、信頼性を重視することが大切です。
【優良業者の特徴】
- 古物商許可番号が明記されている
- 法人運営で、会社名・所在地がしっかり記載されている
- 査定・入金までの流れが明確に説明されている
- 初回は本人確認(免許証など)を求められる
- 無理に急がせるような対応をしない
反対に、「本人確認不要」「LINEだけで即対応」「90%保証」などの宣伝をしている業者は、詐欺やトラブルのリスクが極めて高いと考えてください。
5-3. 個人間売買のリスクと避けるべき理由
X(旧Twitter)やLINE、掲示板などでの「高額買取」や「個人買取」に応じてしまうと、詐欺に巻き込まれる確率が飛躍的に高くなります。
【個人間取引のよくある被害例】
- 「先にコードを送って」と言われて送った瞬間にブロックされる
- 「コードが使えなかった」と文句を言われて支払いを拒否される
- 第三者に転売されて、自分が販売元として責任を問われる
図書カードNEXTのような匿名性の高いギフト券は、個人取引に向いていません。 必ず法人の業者を利用しましょう。
5-4. 買取率の相場と高く売るための工夫
図書カードNEXTの買取率は、他のギフト券と比較するとやや控えめですが、一定の需要があるため安定しています。
【2025年時点の買取相場】
- 約70〜75%前後が主流
【高く売るための工夫】
- コード部分の画像が鮮明で、情報がはっきり見えるように撮影する
- PINコードの未開封部分をしっかり写すことで信頼性が上がる
- 複数業者に相見積もりを取り、条件が最も良いところを選ぶ
また、購入直後のカードほど評価されやすく、使用感がないほど高く売れる傾向があります。
5-5. 現金化前に確認すべきチェックリスト
実際に現金化を申し込む前に、トラブルを避けるために以下の項目をチェックしておきましょう。
【現金化前チェックリスト】
・PINコードおよびQRコードがはっきり写っているか?
・カードの状態が良好か(折れ・汚れ・ぼかしなし)
・買取業者が古物商許可を持ち、法人名義で運営されているか
・査定額や手数料が明記されているか?口頭・チャットだけで進まないか?
これらをしっかり確認することで、安心・安全な現金化が実現できます。
次は、図書カードNEXTに関してよくある疑問やトラブルについてわかりやすく解説するQ&A(10項目)をお届けします。
よくある質問(Q&A)

Q1. 図書カードNEXTはどこで使えますか?
A. 全国の図書カードNEXT加盟書店で、書籍・雑誌・一部の文房具などの購入に利用できます。使える店舗は公式サイトの「使えるお店」検索ページで確認可能です。
Q2. PINコードやQRコードがあれば誰でも使えますか?
A. はい。登録なしで利用できるため、PINコードとQRコードを知っていれば誰でも使用可能です。そのため、取り扱いには十分な注意が必要です。
Q3. 残高確認はどこでできますか?
A. 図書カードNEXTの公式サイト(https://www.toshocard.com/)にアクセスし、「残高照会」からPINコードを入力することで確認できます。
Q4. 登録制ではないということは、紛失しても補償はないのですか?
A. その通りです。登録や所有者情報の紐付けがないため、紛失・盗難・不正使用に対しての補償はありません。 取り扱いには細心の注意を。
Q5. 使用済みかどうかを確認する方法は?
A. PINコードを使って残高照会をすれば、残高が0円であれば使用済みと判断可能です。ただし、使用直後でないと履歴は曖昧になる場合もあります。
Q6. ギフトカードで支払いを求められたのですが本物ですか?
A. いいえ、100%詐欺です。図書カードNEXTを含むギフト券での支払いを求める連絡はすべて無視し、ブロックまたは通報してください。
Q7. 残高照会のページが複数出てきてどれが本物か分かりません。
A. 本物のページは必ずhttps://www.toshocard.com/ から始まります。検索エンジン経由ではなく、ブックマークや公式サイトから直接アクセスするのが安全です。
Q8. 図書カードNEXTは現金化できますか?
A. 未使用でPINコードが有効なものであれば、ギフト券買取業者で現金化可能です。個人間取引ではなく、信頼できる業者を利用してください。
Q9. フリマアプリで売るのは違法ですか?
A. 違法ではありませんが、多くのフリマアプリではギフト券類の出品を規約で禁止しています。アカウント停止やトラブルのリスクがあるため、推奨されません。
Q10. 使用後に誰かにコードを見せてしまったけど大丈夫?
A. 使用済みであれば再利用はできません。ただし、悪用されるリスクはゼロではないため、コードや残高履歴は原則として他人に見せないようにしましょう。
まとめ
図書カードNEXTは、スマホで残高確認や利用ができる便利な電子ギフト券ですが、その利便性ゆえに詐欺や不正利用の対象になりやすい面もあります。
特に「登録なしで誰でも使える」「残高が外部から確認できる」といった仕組みが、詐欺グループにとって都合のよい特徴となっているのです。
万が一被害に遭ってしまった場合は、証拠の保存・公式サイトへの早期連絡・警察や消費者センターへの相談をセットで行うことが大切です。
また、現金化したい場合は信頼できる買取業者を利用し、個人間取引は避けるのが安全な選択です。
正しい知識と冷静な判断で、自分の資産と大切な人を守りましょう。



とは?使い方・チャージ方法・対応店舗・注意点まで徹底解説!後払いにも対応したVisaプリペイドカード-120x68.png)